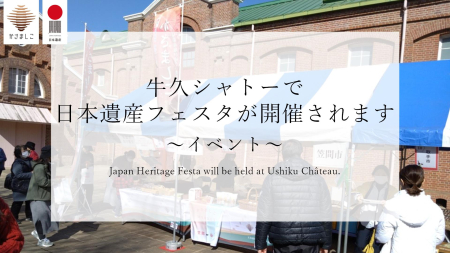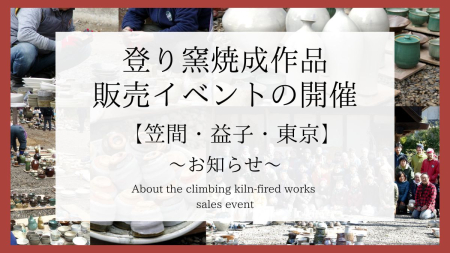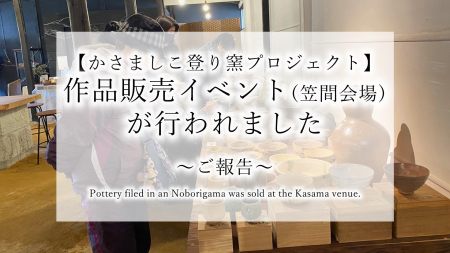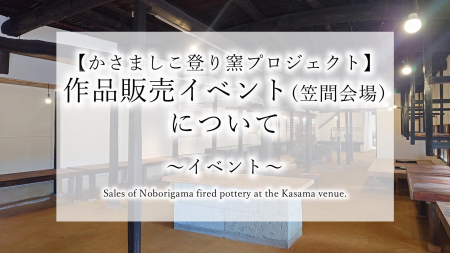兄弟産地が紡ぐ〝焼き物語〟
日本遺産 認定!
「かさましこ」とは?
かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”~
日本遺産に認定されたストーリー
Topic
イベント・お知らせ
コラム
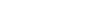
かさましこの日本遺産に会いに行ってきました!
コース
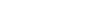
兄・笠間をめぐる?弟・益子をめぐる?
構成文化財
日本遺産に登録されている構成文化財をご紹介します。
日本遺産 かさましこ 兄弟産地が紡ぐ〝焼き物語〟
令和2年度「日本遺産魅力発信推進事業」